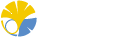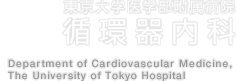診断、治療技術の進歩に伴い、先天性心疾患患者の生存率は飛躍的に向上し、9割以上の患者が成人に達することができるようになっています。その結果、成人先天性心疾患(ACHD)患者は増加の一途をたどっています。ACHD患者は、医学的、社会的に様々な問題をかかえており、心臓の管理はもちろん、小児科から成人診療科への移行や患者教育、就職、妊娠出産、成人発症の疾患の合併など多面的な問題に対処していく必要があります。
当院はACHDの専門医修練施設であり、5人以上のACHD専門医が常駐しています。循環器内科医を中心に、心臓外科、および小児循環器科と連携してACHD専門医チームを作り、Fontan術後を含む複雑なACHD術後患者の管理、ハイリスク妊娠出産の管理、肺高血圧合併シャント性心疾患の管理や治療、再手術の適応評価や管理、重症心不全(移植や補助人工心臓含む)などを行っています。豊かな経験と実績から、高度で最先端の医療を提供し、ACHD患者さん1人1人の人生を長期的によりよくできるようにと考えて日々診療を行っています。
また、心房中隔欠損症、動脈管開存症、卵円孔開存症のカテーテル閉鎖術に加え、ファロー四徴症術後の肺動脈弁逆流に対する経皮的肺動脈弁留置術(Harmony Valve)にも対応しています。